自給自足生活を計画する理由
消費を見つめ、コストを勉強する
日々の生活の中で、必需品というものがあり、その必需品はきっと人それぞれ違うと思います。

僕は化粧水は必要ないし、服もそんなに必要ないな
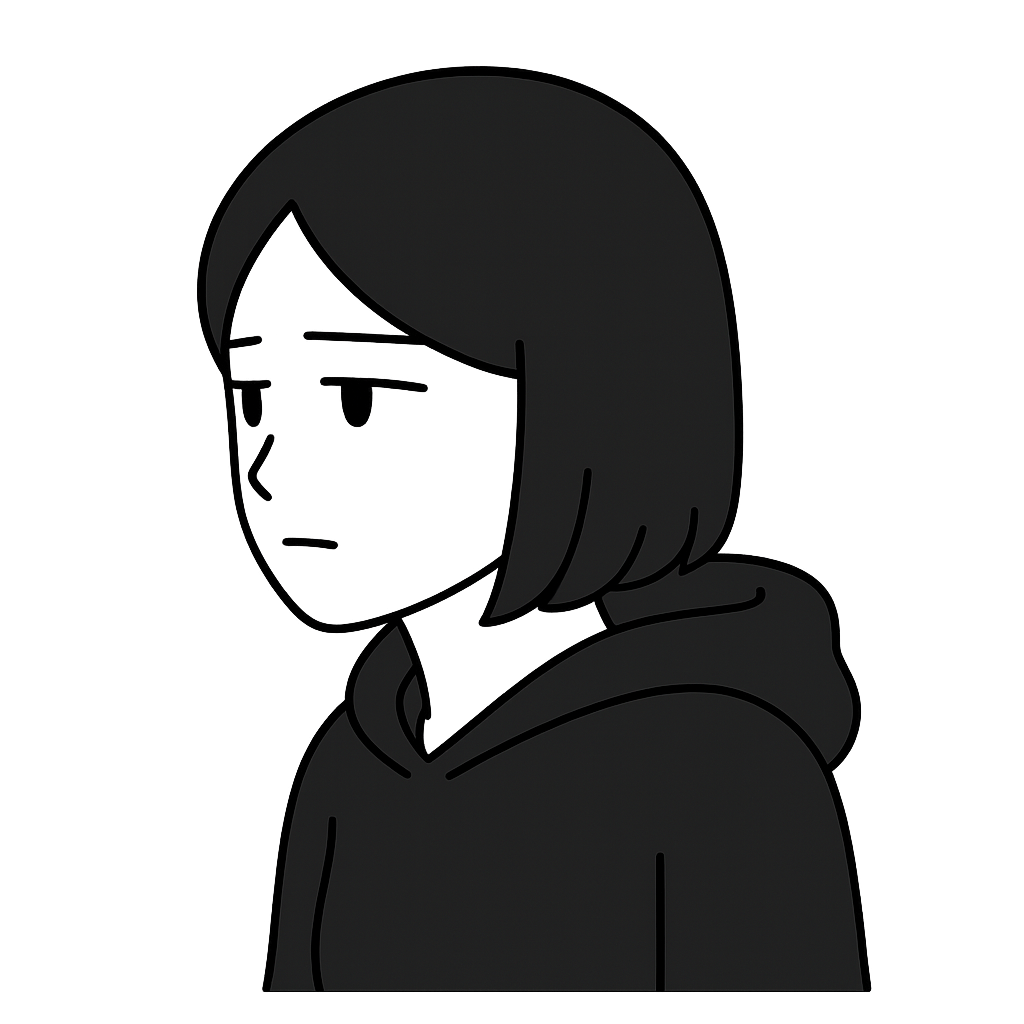
私は化粧水は絶対必要だし、服だって「普通」には欲しい
そう
「普通」はみんなそれぞれ違うのです。
さらに、みんな欲しがるものが、「需要」。その「需要」のあるものを作るにもコストが掛かる。
さらには物流のコスト…
つまりは、末端の消費者に届くのには、かなりのコストが掛かる
食べ物の場合だってそうだ。少し考えてみよう
各コストについて
生産コスト(農家・漁師・畜産農家など)
ここが一番の出発点です。
- 種・苗・飼料・肥料・農薬などの資材費
- 土地利用費(農地の賃借料や固定資産税)
- 人件費(家族労働・雇用労働)
- 機械・設備の購入や維持費(トラクター、ハウス、給餌設備など)
- 水道・電気・燃料などの光熱費
- 保険料(作物保険、家畜保険)
ここで作られた食材の「出荷価格」が最初の原価になります。
集荷・加工・一次流通コスト
収穫物はそのままでは市場に出せないことが多いです。
- 選別・洗浄・包装
- 冷蔵・冷凍保管(フードチェーン維持)
- 輸送費(トラック、船、航空機など)
- 卸売市場や集荷場での手数料
- 加工コスト(精米、カット野菜、冷凍食品、肉の解体など)
→ ここで「卸売価格」が形成されます。
卸売・物流コスト
- 市場での仲買人のマージン
- 再度の輸送(市場から各地の倉庫や店舗へ)
- 倉庫保管料(冷蔵・冷凍倉庫代も高額)
- 輸入食品なら通関費用・関税
小売(スーパー・コンビニ・飲食店)
小売段階でのコストはかなり大きいです。
- 店舗の賃料や光熱費
- 店員の人件費
- 商品の廃棄ロス(売れ残り・期限切れ)
- 広告宣伝費(チラシ、CM、割引セールなど)
- 在庫管理やシステム維持費
→ 小売はこれらを上乗せして「販売価格」をつけます。
消費者に届くまで
最終的に消費者が支払う金額には、
- 上記すべてのコスト
- それぞれの段階の事業者の利益(マージン)が含まれています。
イメージ例(仮にリンゴ1個100円で売られている場合)
- 生産者の手取り(農家):20〜30円
- 集荷・加工・輸送:20円
- 卸売・物流:10〜15円
- 小売コスト+利益:35〜50円
→ 消費者価格:100円
(実際には食品や産地・流通の仕組みで大きく違います)
まとめ
- 生産段階は「原価」に近いが利益は小さい
- 輸送・物流・保存・廃棄リスクのコストが意外に大きい
- 小売は「店舗運営コスト」と「利益」を上乗せする
- 消費者が払う価格の中で、生産者に届くのは全体の2〜3割程度になることが多い
確かに必要なコストは存在していて、なんでも安価に届けられ、生活は豊かになったと思われています。しかし、現実はどうでしょうか?

化粧水とか変な例を出してすまぬな。妻よ
この、コストについて言及したかったんだ
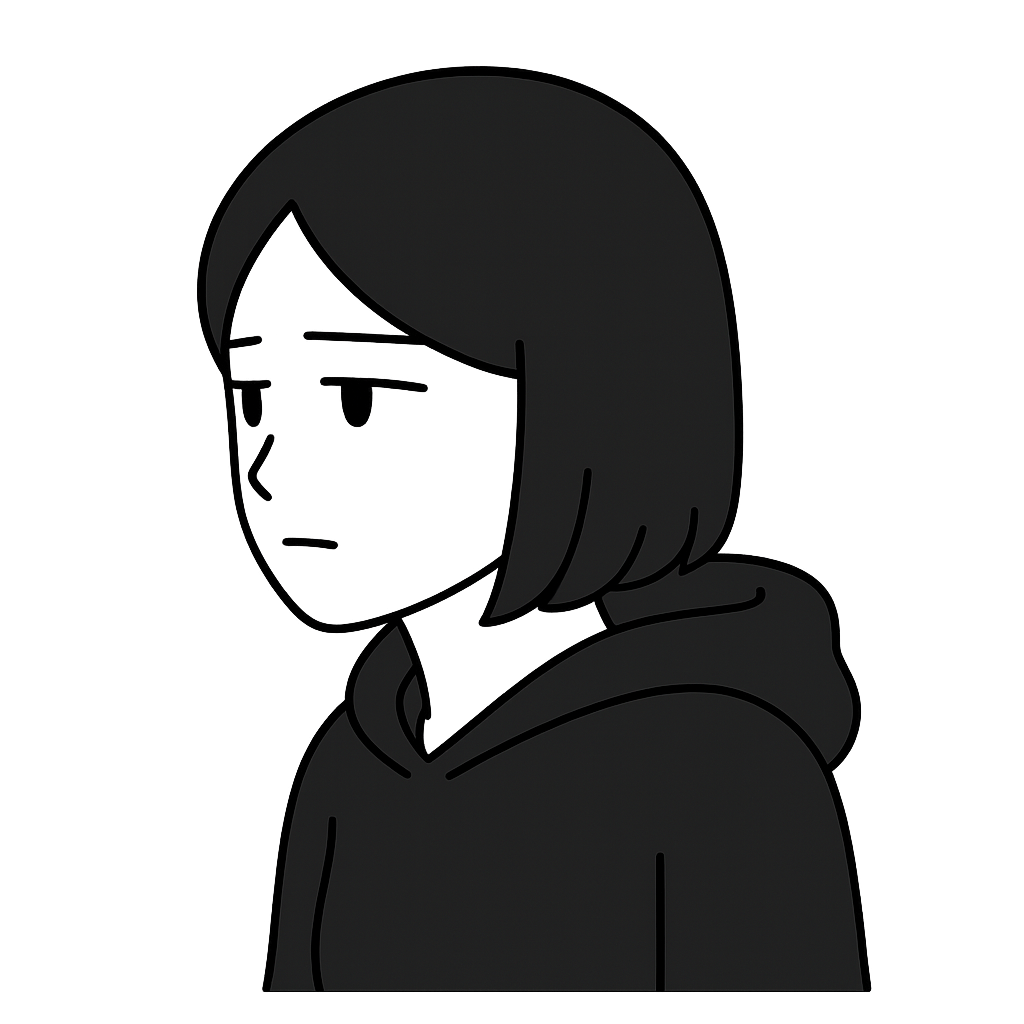
うん、なんとなく言いたいことはわかったけど
要は、地産地消して小規模で経済を盛り上げたらどうか?
近くで生産されていない物はもっと高くてもいいのでは?
ということかな?

そう、そして自分で作って消費する分を作るんだ
それが、生きるための仕事、労働コストになるけど、それは直接自分の生きる為の労働となる。つまりは経済の奴隷ではなくなるってわけだ
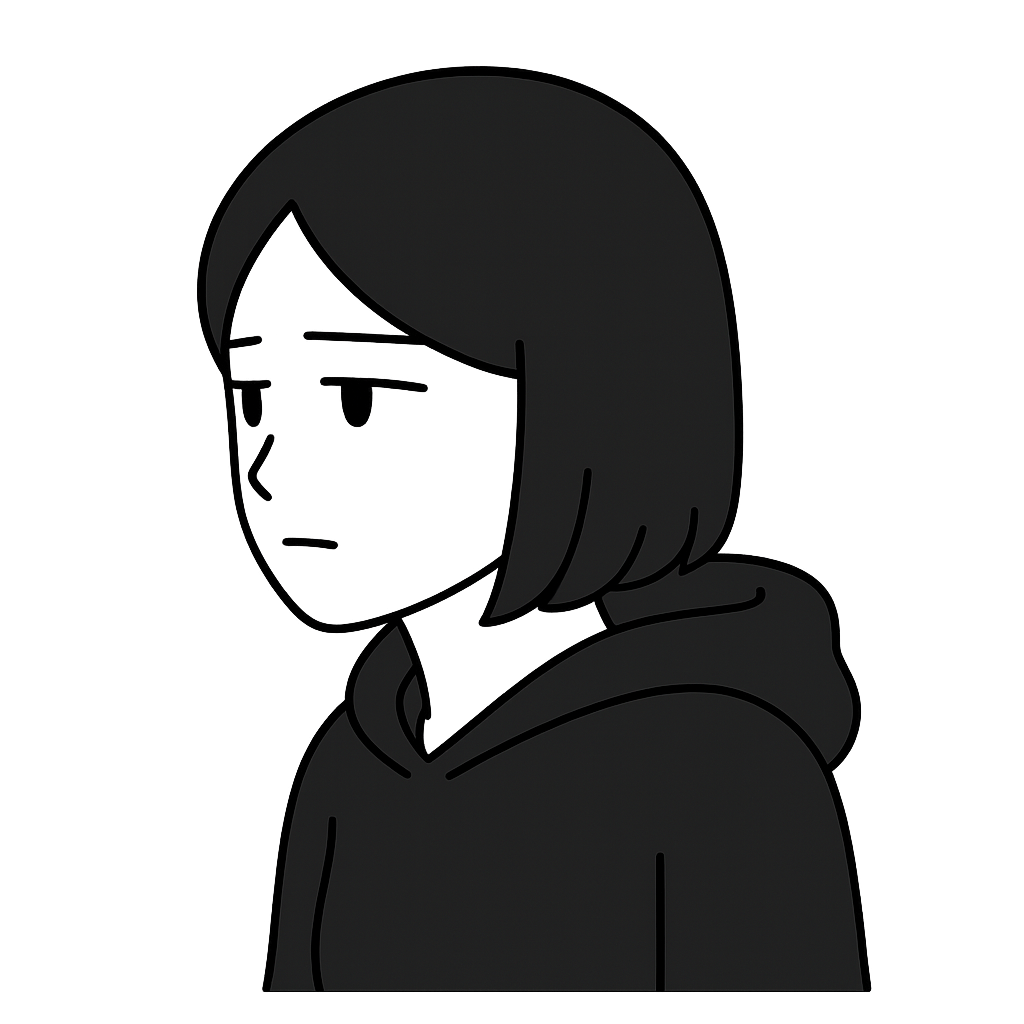
でも、それだけでは他の物、特に高価なもの手に入らなくならない?
例えば、メガネとか、時計とか、スマホとか…

確かにその通りだ
ただ、足るを知るということを覚えれば、なんでも必要と物が増え続けることはなくなるぞ
半農という考え、自然農法、協生農法との出会い
現代社会では生きるためには、食べ物を作るだけでは生きてはいけない。
特に、野菜を作りたくとも、土地もない。農家ではないから農地も借りられない。ならば農地じゃないところでも出来ないかと考えていると
自然農法、協生農法なるものを見つけました。

おお!これはすごい
なんもしないでも、生えてる!
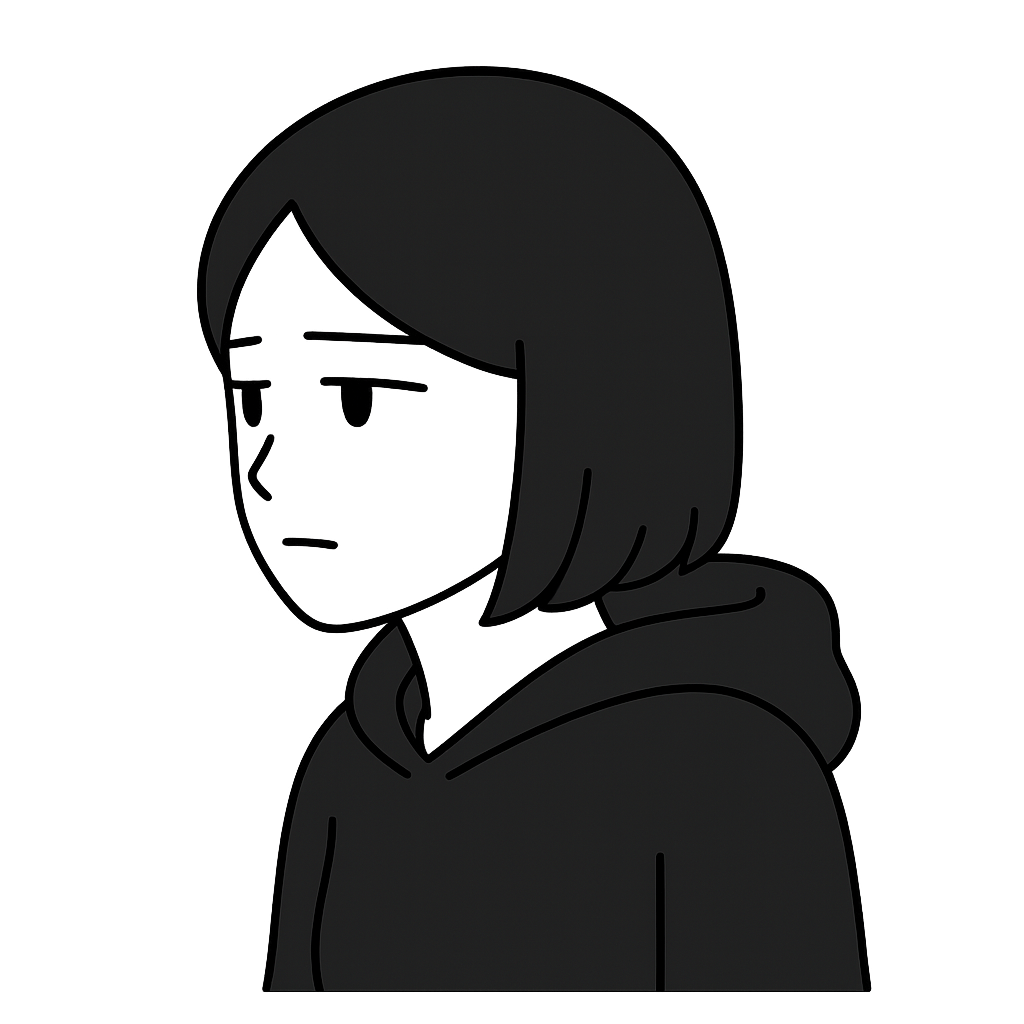
うーん、これは誰でも出来そうで、激しく難しいやつだと思う

え?だって雑草もさもさで、適当そうじゃん
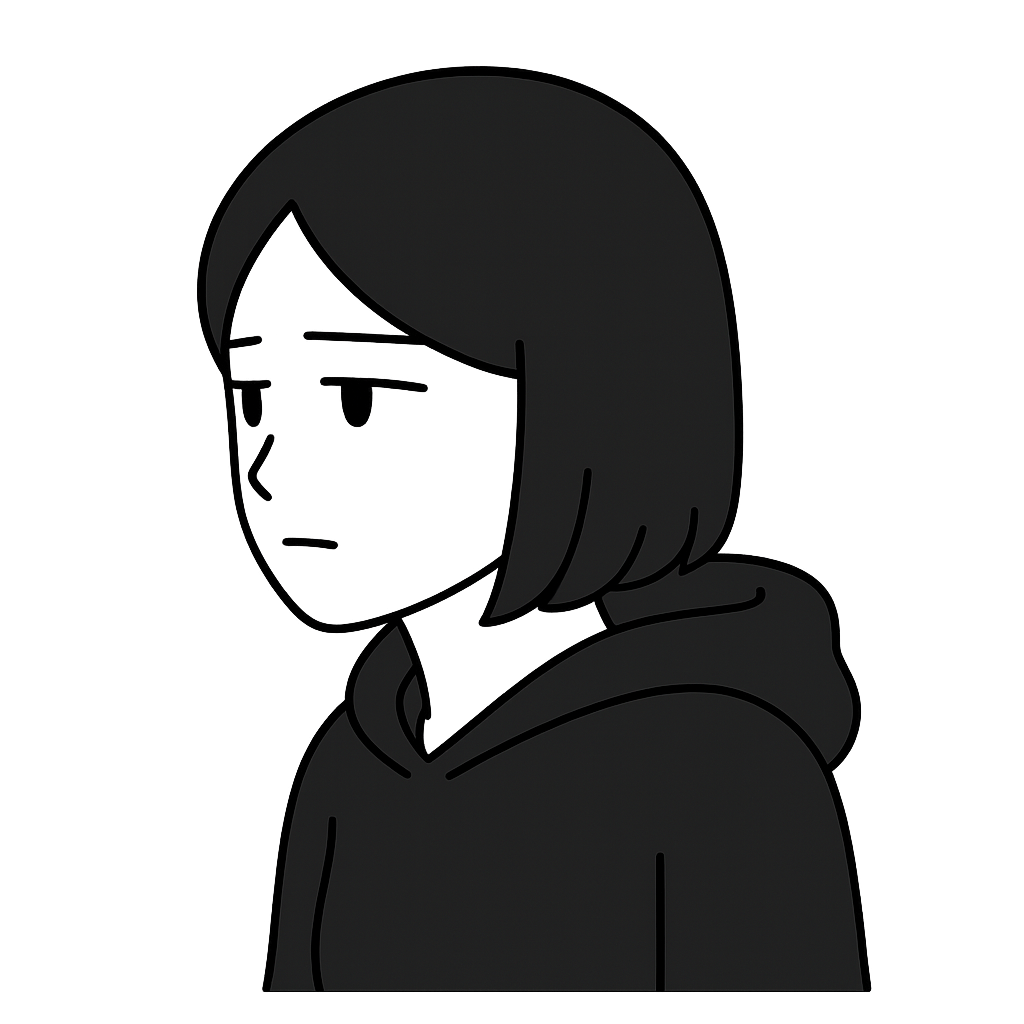
そうじゃない。
これは、小さな生態系を作っている感じだと思う
しかも、土の中の微生物込みで考えている。ほとんど芸術じゃないかな

む、難しいね?
これまでは、生産量や流通を考え、効率よく行っていた農業。その効率よりも生態系を重視した農法で、野菜を野生に帰していく方法のようだ。

ちょっと、1から農業について学びたいな
というか、すぐには出来ないなら、生産コスト段階で関わってみたいな
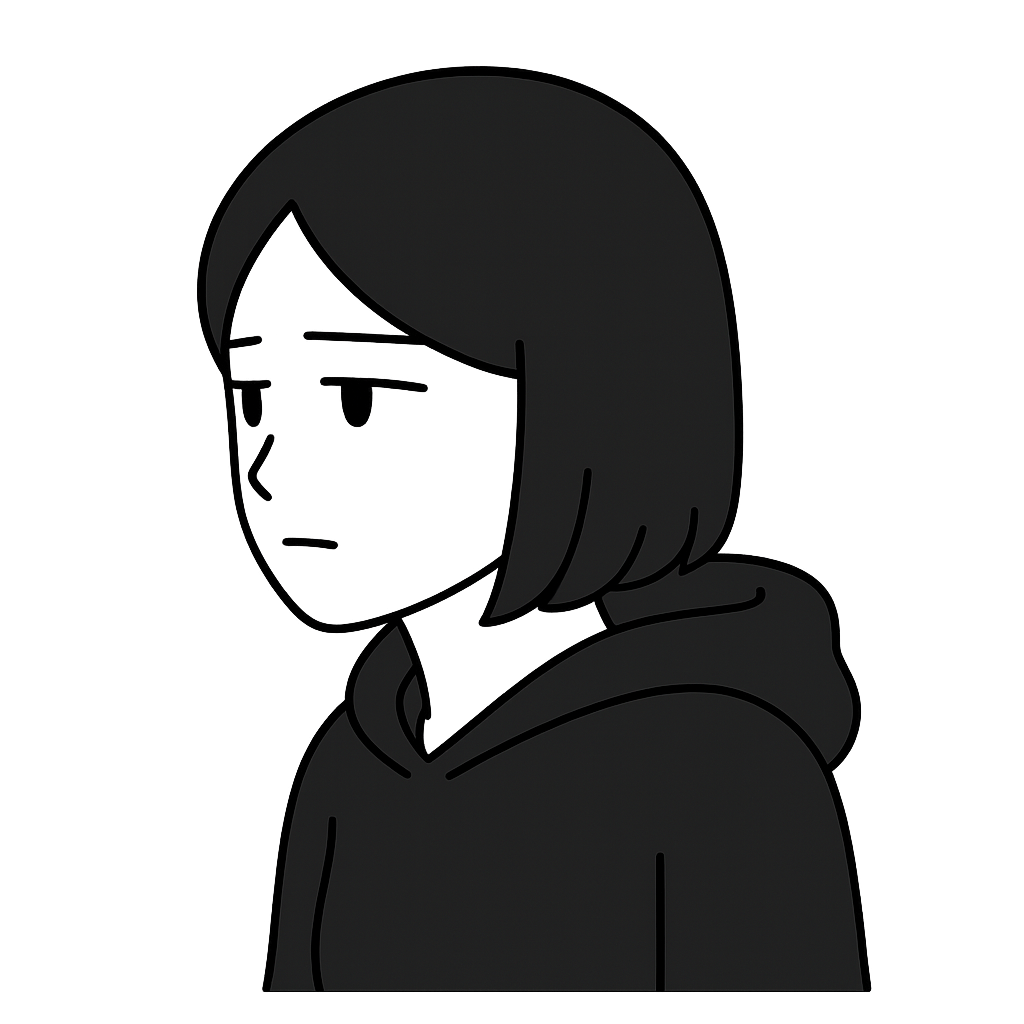
(お、働く気になったか?)
こうして、いずれ協生農法で自分たちの食べる分を用意するという長ーい旅が始まったのである。




コメント