はじめに:当時の僕に伝えたい、たった一つのこと

やあ!今回は、僕がかなりお金と時間をかけた趣味、ボルダリングについて話すよ!
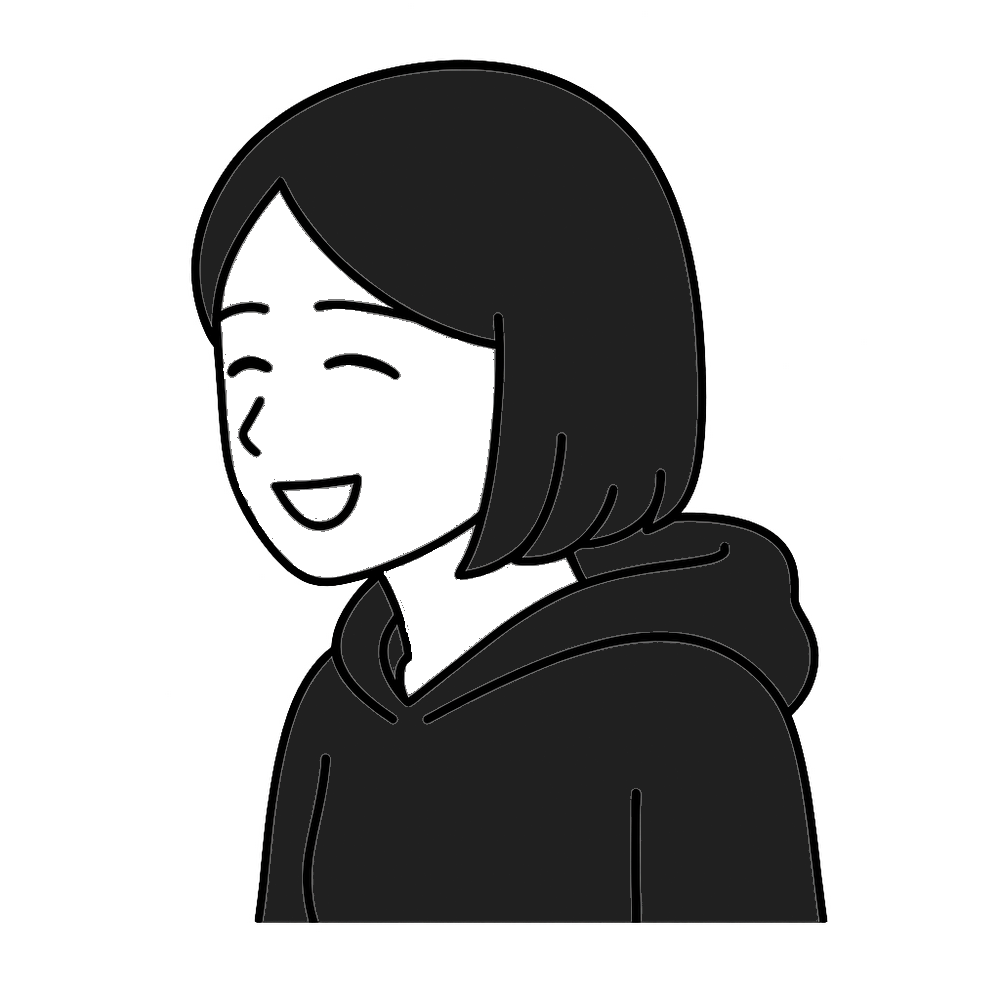
最近、また始めようかなって言ってるもんね

そう!それで、気づくのに時間が掛かった事と、それを育てるのに時間がかかることを今回シェアしておきたいなと思って!
初めていきますか!
ボルダリングを始めて2〜3ヶ月の頃、プロテインを飲みまくったり、ひたすら腕立て伏せや懸垂をしていませんでしたか?「筋力がないから登れない」と思っていませんか?
もしそうなら、この記事はきっと役に立つはずです。
5年間本気でボルダリングに取り組み、僕が一番学んだのは「筋力より、工夫する力が大切」だということ。そして、その考えこそが、ボルダリングを何歳になっても楽しめる鍵でした。
今回は、僕が5年かけて見つけた「工夫の秘訣」を、初心者のみなさんに伝えていきたいと思います。
筋力は必要ない?ボルダリング初心者がぶつかる壁
ボルダリングで登れない課題は、筋トレで解決するものではありません。それはまるで「謎解き」です。腕力で無理やり登ろうとして腕がパンプしてしまうのは、体が「そのやり方は非効率だよ」と教えてくれているサインです。

パンプは腕が張る事だよ。初心者だけじゃなくてもなるけど、このパンプとの付き合い方が重要なんだよ
僕も最初はそうでした。がむしゃらに力任せで登ってばかり。でも、日本で出会ったベテランクライマーの方や、海外で出会った強いクライマーたちは違いました。彼らは重い筋肉を嫌い、体幹(インナーマッスル)、そして腱の強さを意識していました。
大切なのは、「どうしたら楽に、効率よく登れるか?」という視点に切り替えること。
私がよく例えるのは、自分の体を一つのハンガーと見立てて、岩のクリンプに引っ掛けながら登っていくイメージです。
筋力はそのための「道具」にすぎず、必要なのは「全身を使って効率的に体を運ぶ」という工夫です。パンプ対策は、毛細血管を増やすマラソン選手のように、反復練習で持久力と耐久力を高めることで解決します。
筋力より大切な3つの「工夫」練習法
筋力に頼らず「工夫」して登るには、いくつか具体的な練習法があります。これは僕が5年かけて見つけた、本当の上達に欠かせない3つの要素です。
自分の体を知る(体との対話)
一番のおすすめは、付箋を壁に貼り「目を閉じて付箋にタッチする」練習です。頭の中で「あのホールドに手を伸ばそう」とイメージした場所に、実際に手が届いているかを確認します。
- 「思ったより足が遠い」
- 「手を伸ばしすぎるとバランスが崩れる」
こんな風に、頭の中のイメージと現実の体の動きを一致させる練習をすることで、自分の体のリーチや重心の位置を感覚的に把握できるようになります。これこそが、無理のない効率的なムーブを組み立てるための第一歩です。
柔軟性と体幹を鍛える
柔軟性は、前屈のように体を柔らかくすることだけではありません。足首、股関節、手首、肩といった関節の柔軟性も同じくらい大切です。体幹(インナーマッスル)は、全身を安定させ、手足の力を効率よく伝えるために不可欠な要素です。
体を一つのハンガーと見立て、引っ掛けるように登るためには、関節がスムーズに動き、中心がブレないことが不可欠なのです。
【初心者でもできるトレーニング】
- プランク: うつ伏せになり、両肘とつま先で体を支え、頭からかかとまで一直線になるようにキープします。体幹全体を強化する基本中の基本です。
- サイドプランク:体の側面を下にして横になり、片方の肘と足の外側で体を支えます。体幹の横側(腹斜筋)を鍛えることで、ダイナミックな動きやバランスを要するムーブに強くなります。
- ブリッジ(ヒップリフト): 仰向けになり、膝を立ててお尻を持ち上げます。お尻と背中を一直線に保つことで、股関節周りの柔軟性と体幹を同時に鍛えることができます。
- ストレッチ: ボルダリング前後に、股関節や肩甲骨周りをしっかり伸ばすことで、可動域が広がり、怪我の予防にもつながります。
※ これらを目を瞑って行ってみてください。特にサイドプランクがおすすめです。体幹がブレブレになるのでそれを抑えると、実際の登りでも安定します。
腱は鍛えようと思っても無理をしてしまいがちなので、怪我をしないように少しずつ、柔軟な体と強い体幹を作ることが重要です。
ストレッチについては、動的ストレッチを癖になるくらい行うことをお勧めします。
オブザベーション能力を磨く(事前に思考する)
ボルダリングは登る前の「オブザベーション(観察)」がとても重要です。登る前にただ課題を眺めるのではなく、「自分ならどう動くか?」を具体的にシミュレーションします。
- 「足はここに置く」
- 「次は右手を出す」
- 「このホールドは指先だけで持つ」
このように頭の中で実際に登ってみることで、「自分がやろうとしていること」と「現実にできること」のギャップを埋めることができます。自分の体を知っていれば、「このムーブは今の自分には難しいから、別の方法を探そう」といった現実的な判断もできるようになります。この段階で、ようやく自分に足りないもの(柔軟性なのか、体の使い方なのか)が見え始めてきます。
これが進んでいくと、「あのホールドは◯◯な感じだから、足のほうが重要そう」など自分の中で考えを巡らせて実現していく、確かな自信につながります。
まとめ
上達は挑戦の数!ボルダリングは工夫で楽しくなる
ボルダリングの上達は、短期間で急に力がつくものではなく、一種のサイクルだと考えています。「登れない」という壁にぶつかったら、「課題を分析 → 補強 → 再挑戦」のサイクルを繰り返すこと。
最初の一歩は失敗の連続です。でも、その失敗は「筋力が足りないから」じゃなく、「まだその課題の解き方が見つかっていないだけ」。もし、課題を前にして「怖い」という気持ちが勝るなら、無理をする必要はありません。それよりも、どうやったら登れるかを工夫することの楽しさを見つけてほしいです。そのトライの数が、いつの間にかあなたの成長につながっているはずです。
5年を経て僕が一番大切だと気づいたのは、ボルダリングは「力を競うもの」ではなく「頭と体を使って解くパズル」だということ。そして、その過程を心から楽しめる人が、ずっと強く、そして何歳になっても登り続けられるクライマーになれるのだと思います。
こちらの記事もどうぞ

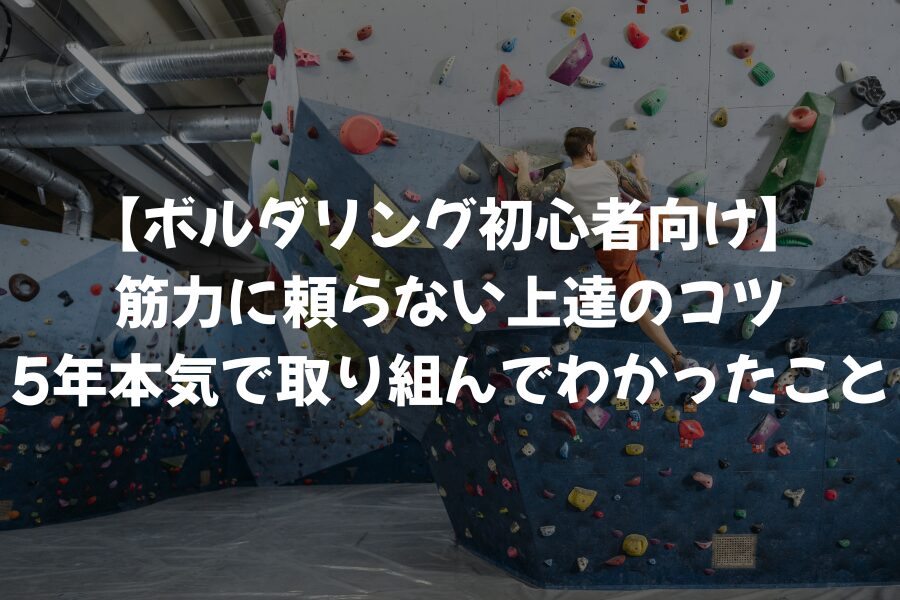
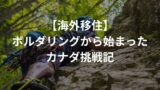


コメント